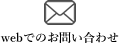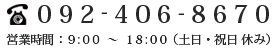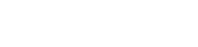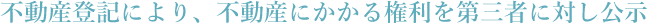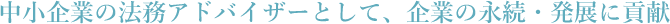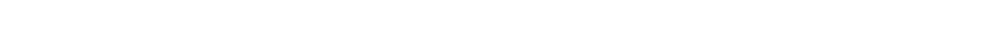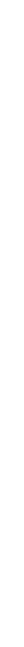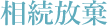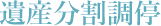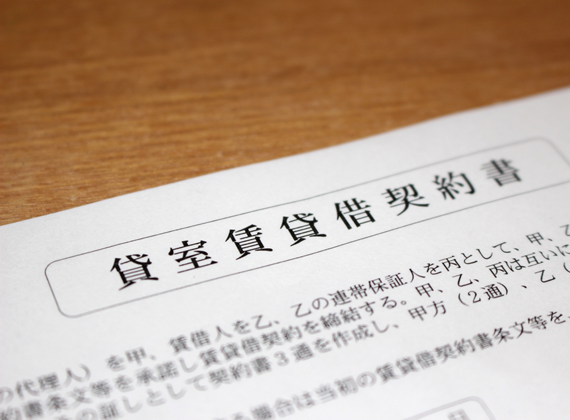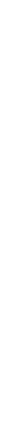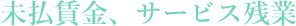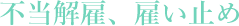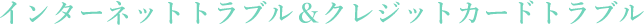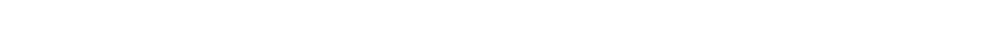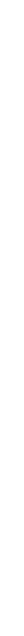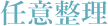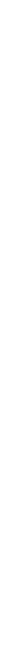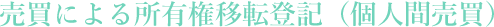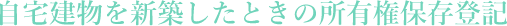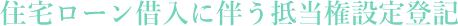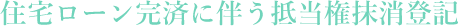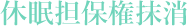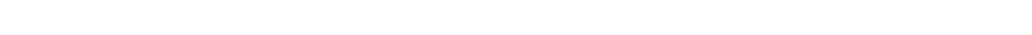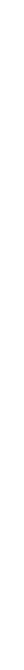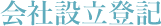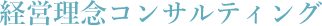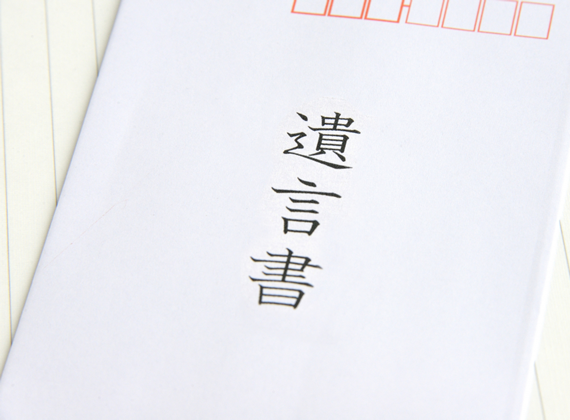
① 公正証書遺言
(費用例)
*預金1000万円を、子ども1人に対して、公正証書遺言で遺贈する場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 10万円 | ||
| 公証人手数料 | 2万8000円 | ||
| 戸籍等取得費用 | 6000円 | ||
| 合計 | 10万円 | 3万4000円 | 相談料込 |
② 遺言書の検認
なお、自筆証書遺言の作成に関するご相談についてもお気軽にご相談ください。
(費用例)
*自筆証書遺言の検認申立てを行い、不動産(評価額 1000万円)を相続する場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 遺言検認申立書作成 | 4万円 | ||
| 検認申立書印紙代 | 800円 | ||
| 戸籍等取得費用 | 6000円 | ||
| 相続登記申請 | 5万6000円 | ||
| 登録免許税 | 4万円 | 評価額の0.4% | |
| 合計 | 9万6000円 | 4万6800円 | 相談料込 |
③ 遺言執行者
(費用例)
*相続財産の総額が300万円以下の遺言について、遺言執行者に就任する場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 遺言執行者就任 | 30万円 | 財産調査料込 | |
| 合計 | 30万円 | 相談料込 |
※ただし、裁判などを行う場合は事件類型ごとの報酬基準に従います
(費用例)
*被相続人である父の財産及び債務を長男が単独で引き継ぐために、残された子ども2名のうち、
下の弟が相続放棄を行う場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 相続放棄申述書作成 | 5万円 | ||
| 相続放棄申述書印紙代 | 800円 | ||
| 戸籍等取得費用 | 5000円 | ||
| 連絡用切手代 | 820円 | ||
| 合計 | 5万円 | 6620円 | 相談料込 |
後の世代に相続問題を残さないために、不動産を所有している方が亡くなられた際には、早急に不動産の名義を相続人に移転する事をお勧めしております。遺産分割協議や寄与分にかかる問題も合わせてご相談ください。
(費用例)
*不動産(評価額1200万円)の相続手続の場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 相続登記申請 | 5万6000円 | ||
| 登録免許税 | 4万8000円 | 評価額の0.4% | |
| 戸籍等取得費用 | 6000円 | ||
| 連絡用切手代 | 5000円 | ||
| 合計 | 5万6000円 | 5万9000円 | 相談料込 |
(費用例)
*預金(700万円)及び有価証券(300万円)の相続手続の場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 相続登記申請 | 20万円 | 残高の2% 調査料込 | |
| 戸籍等取得費用 | 6000円 | ||
| 連絡用切手代 | 5000円 | ||
| 合計 | 20万円 | 1万1000円 | 相談料込 |
(費用例)
*相続人3人で遺産分割調停を行う場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 遺産分割調停申立書作成 | 5万円 | ||
| 印紙代 | 3600円 | ||
| 戸籍等取得費用 | 5000円 | ||
| 連絡用切手代 | 5000円 | ||
| 合計 | 5万円 | 1万3600円 | 相談料込 |
また、不在者自身の代理人として、遺産分割等の法律行為や財産管理を行う手続きが、不在者財産管理人制度です。当事務所では、相続財産管理人や不在者財産管理人の選任申立手続、財産管理人への就任により、ご家族の方々をトータルにサポートいたします。
(費用例)
*相続人が一人もいないときに、利害関係人からのご依頼により相続財産管理人選任申立を行う場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 相続財産管理人選任申立書作成 | 5万円 | ||
| 印紙代 | 800円 | ||
| 戸籍等取得費用 | 5000円 | ||
| 官報広告料 | 3670円 | ||
| 連絡用切手代 | 5000円 | ||
| 合計 | 5万円 | 1万4470円 | 相談料込 |
(費用例)
*海難事故で行方不明になったご家族の地位を法律上の死亡として確定させる場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 失踪宣告審判申立書作成 | 7万円 | ||
| 印紙代 | 800円 | ||
| 官報広告料 | 4179円 | ||
| 連絡用切手代 | 820円 | ||
| 合計 | 7万円 | 5799円 | 相談料込 |
法的に離婚が認められるためには、
①配偶者の不貞行為、
②配偶者からの悪意の遺棄、
③配偶者が3年以上生死不明、
④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない、
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
のいずれかの事情が必要であり、裁判上これらを主張するためにはその証拠が必要となります。
一方、法的な離婚事由が存在しない場合に離婚を成立させるためには、お互いが話し合いを行うことで協議離婚を成立するしかありません。
離婚に伴うトラブルには、相手方に関すること(慰謝料及び財産分与)、子どもに関すること(親権及び養育費)、その他事務手続(氏に関すること、公正証書を作成するか否か等)が存在します。
事実関係の整理、互いの有責の程度の整理、慰謝料の算定等を行った上で、示談案提案、公正証書による離婚、離婚調停申立書作成等の方法により、離婚トラブル解決の最善の提案をいたします。
高齢者やその家族などが安心して生活をおくるために、成年後見申立から終了までご依頼者に合った適切なサポートを行います。
(費用例)
*認知症の方のご家族からの依頼により、成年後見申立を行う場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 成年後見申立書作成 | 10万円 | 関係書類取得報酬込 | |
| 印紙代 | 800円 | ||
| 後見登記手数料 | 2600円 | ||
| 連絡用切手代 | 3380円 | ||
| 合計 | 10万円 | 6780円 | 相談料込 |
医師の実費として5万円程度の鑑定料がかかります。
成年後見人就任報酬 司法書士が実際に行った業務に応じて、家庭裁判所が報酬額を決定します。
通常1か月あたり2~3万円程度の金額となります。
ご自身が元気な間はご自身で管理し、ご自身が衰えた際には受託者の管理に移行させる事ができる後見代用信託では、第三者としての家庭裁判所の監督に臥さないため、信頼できる家族としての立場でご本人のために運用していただく事が可能となります。
また、遺言代用信託では、第2次第3次に渡って財産を譲り受ける方を指定できるなど、通常の遺言よりも柔軟に遺言を活用することが可能です。
ご相談に応じてオンリーワンの信託設計を行いますので、費用のお見積もりは個別の事情をお聞きしてからとなります。
また、争いとなっている金額が140万円を超える場合には、案件に応じて弁護士の先生に引き継ぐか(当事務所では、紹介料は一切いただいておりません。)、又はご本人に法廷に立っていただき、当事務所では訴状や準備書面を作成する事で訴訟支援を行い、法律紛争の解決をサポートいたします。
(民事紛争手続報酬の目安)*実費は除く
| 着手金(紛争額140万円以下) | 2万5000円 |
|---|---|
| 訴訟に移行した場合の追加着手金 | 2万5000円 |
| 成功報酬(訴訟を行わなかった場合) | 現実利益の10% |
| 成功報酬(訴訟を行った場合) | 現実利益の20% |
| 強制執行手続(勝訴後支払のない場合) | 7万円 |
| 内容証明を作成した場合の追加報酬 | 2万円 |
*ご相談の際、労働契約書、雇入通知書、給与明細、タイムカードなどをご用意ください。
労働者側に帰責事由のある解雇を、「普通解雇」や「懲戒解雇」と言います。また、会社側が、人員削減や業績不振を理由に解雇するものを「整理解雇」と言いますが、いずれの場合の解雇も、個別の事情を考慮した上で有効な解雇か否かを判断します。
不当解雇は、法律上無効です。当事務所では、労働者の地位確認請求を求める訴訟、労働審判、民事調停手続等により、解雇無効期間の賃金請求、復職、退職と引換にする金銭解決等を求めていきます。
*ご相談の際、労働契約書、給与明細、解雇理由証明書、解雇予告通知書、退職証明書等をご用意ください。
悪質な訪問販売業者から、意に沿わない買い物をしてしまった場合には、内容証明郵便によるクーリングオフ、民事訴訟による代金返還請求等を行い、被害の回復を図ります。
*ご相談の際、契約書の控え、販売員の名刺、購入日時記録等をご用意ください。
敷金は、原則として退去時には全額賃借人に返還すべき性質の金銭であり、部屋の修繕費は、原則として賃貸人が負担すべき性質の費用です。
近年、最高裁判決により、一定の事情があれば敷引特約を有効とするなどの賃借人にとって不利な判決も出されておりますが、賃貸人が賃借人に対して、理由のない敷引や修繕費請求を一方的に行うことは違法です。
訴外交渉、民事調停手続や民事訴訟手続により、賃貸借トラブル解決ための最善の方法を図ります。
*ご相談の際、賃貸契約書、賃料の支払通帳、部屋の写真等をご用意ください。
取引の相手方が見えない状態で決済が完了してしまうため、トラブルが発生した時には、まず相手方を探し出す事から始めることも多い問題です。
特定商取引法、消費者契約法、資金決済法及び割賦販売法並びにクレジットカードに関する国際規約等を駆使して、相手方との訴外交渉、訴訟提起等により被害の回復を図ります。
*ご相談の際、サイト記録、メール記録、クレジットカード、支払明細等をご用意ください。
- ・ネットショッピングをしたら、写真と違う物品が届いた(全く届かない)。
- ・通販で未成年の子どもが勝手に高額な買い物をしてしまった。
- ・財布を亡くしたときに、勝手にクレジットカードを使われた。
- ・出会い系サイトに登録したが、全く会えずにいる。サクラサイトではないか。
- ・インターネット経由で会社に出資したが、架空の会社のようだ。
- ・未成年の子どもが勝手にクレジットカードを使用して、オンラインゲームに多額の課金をしてしまった。
- ・アダルトサイトに勝手に登録されて、多額の利用料を請求されている。
その上で、加害者か被害者か、過失割合、人身事故か物損事故か、任意保険に加入しているか否か、通院期間や後遺症の有無等を具体的にお聞き取りいたします。自動車業者の第三者の知見も踏まえた上で、互いの損害額を確定し、交通事故の相手方と、訴外交渉及び訴訟対応により、交通事故紛争の解決を図ります。
法的に離婚が認められるためには、
①配偶者の不貞行為、
②配偶者からの悪意の遺棄、
③配偶者が3年以上生死不明、
④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない、
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
のいずれかの事情が必要であり、裁判上これらを主張するためにはその証拠が必要となります。
一方、法的な離婚事由が存在しない場合に離婚を成立させるためには、お互いが話し合いを行うことで協議離婚を成立するしかありません。
離婚に伴うトラブルには、相手方に関すること(慰謝料及び財産分与)、子どもに関すること(親権及び養育費)、その他事務手続(氏に関すること、公正証書を作成するか否か等)が存在します。
事実関係の整理、互いの有責の程度の整理、慰謝料の算定等を行った上で、示談案提案、公正証書による離婚、離婚調停申立書作成等の方法により、離婚トラブル解決の最善の提案をいたします。
(費用例)
*3社の消費者金融に対して債務が存在しており、返済期日及び返済金額を再設定するために各社の任意整理を行う場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 任意整理報酬 | 6万円 | 2万円/1社 | |
| 連絡用切手代 | 492円 | ||
| 合計 | 6万円 | 492円 | 相談料込 |
(費用例)
*5社の任意整理で、うち1社は法定金利引き直し計算の結果、過払状態となっていたため、過払金返還請求を行い、
訴外で80万円の過払金返還を受けた場合。
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 任意整理報酬 | 10万円 | 2万円/1社 | |
| 過払金報酬 | 12万円 | 返還額の15% | |
| 連絡用切手代 | 820円 | ||
| 合計 | 22万円 | 820円 | 相談料込 |
(費用例)
*5社の消費者金融から合計300万円及び銀行からの住宅ローン1200万円を借り入れているが、住宅を手放したくないため、
住宅ローンは従前のまま支払を続け、消費者金融の支払を減縮するために個人民事再生を行う場合。
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 個人再生申立書作成報酬 | 35万円 | ||
| 個人再生申立書印紙代 | 1万円 | ||
| 個人再生予納金 | 1万1928円 | ||
| 連絡用切手代 | 3240円 | ||
| 合計 | 35万円 | 2万5168円 | 相談料込 |
なお、裁判所において、個人再生申立書の内容を調査するための個人再生委員の選任が必要と判断した場合には、
別途個人再生委員費用として、15万円程度の追加実費がかかります。
債務者が財産を保有する場合には、最低限の財産を残し、借金返済に充てることとなります。免責が得られない場合として、「借金の原因の大半がギャンブルによるものであること」「破産手続きにおいて、裁判所に対し虚偽の報告を行った」等の制限があります。
(費用例)
*10社に対して合計1000万円を借り入れており、現在は無職で財産も無く、完済が不可能のため、自己破産を行う場合
(同時廃止の場合)。
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 破産申立書作成報酬 | 20万円 | ||
| 破産申立書印紙代 | 1500円 | ||
| 破産予納金 | 1万0584円 | ||
| 連絡用切手代 | 492円 | ||
| 合計 | 20万円 | 1万2576円 | 相談料込 |
一方、相手方の請求に応じて少しでも返済をしたり返済の約束をしたりしてしまうと、消滅時効を主張することができなくなってしまいます。消費者金融や消費者金融から債権を譲り受けた会社の中には、これを狙って5年を経過してからでも平気で支払請求を行う会社が存在します。
5年が経過した事による消滅時効の主張さえすれば、返済しなくてよい借金です。当事務所では、内容証明郵便を相手方に送付する事で消滅時効の援用をいたします。
(費用例)
*過去に2社の消費者金融からお金を借り入れていたが、最後の取引から5年が経過しているため消滅時効を主張する場合。
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 内容証明郵便作成 | 4万円 | 2万円/1社 | |
| 内容証明郵便切手代 | 3544円 | ||
| 合計 | 4万円 | 3544円 | 相談料込 |
お金に困ってすぐにでも融資を受けたいと考えた方が、つい利用してしまう事が多いのですが、これらの多くは、「無登録業者」「無店舗」「出資法違反の高金利」というヤミ金業者です。
ヤミ金は犯罪です。絶対に利用してはなりません。利用してしまうと、違法・悪質な取立てに遭い、家族、親戚、職場にまで迷惑を掛け、人生を狂わせる事にもなりかねません。
しかし、もしも利用してしまった場合には、法的な解決が欠かせません。ヤミ金という悪質な業者に対しては、「元金すらも返済不要」という最高裁平成20年6月10日判決が出されています。また、預金口座凍結及び被害回復金分配支払請求により、支払金額の返還を受ける事が可能となる制度が平成20年6月より施行されました。
ヤミ金に対しては、ご本人がヤミ金と一切の関係を絶つために、債務不存在通知、任意交渉、預金口座凍結及び被害回復分配支払請求を行うことで、法的解決を行います。
(費用例)
*チラシを見て1者からお金を借り入れたが、3万円の元金のはずが、
1ヶ月で利息が15万円に膨れあがっていて、ヤミ金対応を行う必要がある場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ヤミ金整理 | 2万円 | 2万円/1社 | |
| 被害回復分配金請求 | 5000円 | ||
| 合計 | 2万5000円 | 相談料込 |

法務局に提出する不動産登記申請にかかる費用は、司法書士報酬及び登録免許税等の実費に分かれます。市民の方々にとって、最も高額な財産とも言える不動産に関する権利を守るため、適切に登記申請を行います。
不動産を購入又は売却するときに、売買代金の支払と同時に、旧所有者から新所有者に登記を変更する登記です。戸建物件だけではなくマンション、投資物件、田畑、山林等であっても、不動産登記により権利関係が公示されます。
不動産の価格は他の財産に比べて高額であるため、購入者は銀行でローンを組んで不動産を購入する事が通常です。また、旧所有者に現在抵当権を設定している場合には、売買代金により旧抵当権の抹消を行います。
不動産仲介業者、金融機関と密に連絡を取り、決済当日に適切に売買取引を成立させるために、関係書類の作成、決済立ち合い、法務局登記申請を行います。
(費用例)
*1200万円の住宅ローンを金融機関から借り入れて、自宅として中古の戸建住宅(評価額500万円)
及び土地(評価額700万円)を購入する場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 所有権移転登記申請 | 4万円 | 関係書類作成報酬込 | |
| 登録免許税 | 12万円 | 住宅家屋の軽減税率摘要がある場合 土地評価額の0.15%+建物評価額の0.3% |
|
| 抵当権設定登記申請 | 4万円 | ||
| 登録免許税 | 1万2000円 | 住宅家屋の軽減税率適用がある場合 債権額の0.1% |
|
| 立会料 | 4万円 | ||
| 売渡証書印紙代 | 200円 | ||
| 住宅家屋証明書 | 1300円 | ||
| 登記簿事前調査 | 670円 | 335円/1通 | |
| 登記事項証明書 | 1200円 | 600円/1通 | |
| 合計 | 2万5000円 | 相談料込 |
当事務所では、不動産売買契約書やその他登記必要書類作成、売買決済の立ち合い、法務局登記申請を行い、不動産の個人間売買をサポートいたします。
(費用例)
*不動産仲介業者を入れずに、200万円で自宅と接している土地(評価額150万円)を隣人から購入する場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 所有権移転登記申請 | 4万円 | 関係書類作成報酬込 | |
| 登録免許税 | 2万2500円 | 土地評価額の0.15% | |
| 個人間売買立会料 | 2万円 | 売買価格の1% | |
| 売買契約書印紙代 | 2000円 | ||
| 登記簿事前調査 | 335円 | 335円/1通 | |
| 登記事項証明書 | 600円 | 600円/1通 | |
| 合計 | 6万円 | 2万5437円 | 相談料込 |
後の世代に相続問題を残さないために、不動産を所有している方が亡くなられた際には、早急に不動産の名義を相続人に移転する事をお勧めしております。遺産分割協議や寄与分にかかる問題も合わせてご相談ください。
(費用例)
*不動産(評価額1200万円)の相続手続の場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 所有権移転登記申請 | 5万6000円 | ||
| 登録免許税 | 4万8000円 | 評価額の0.4% | |
| 個人間売買立会料 | 6000円 | ||
| 売買契約書印紙代 | 5000円 | ||
| 合計 | 5万6000円 | 5万9000円 | 相談料込 |
建物を新築することは、所有権を原始取得(最初から自分のもの)する事であり、不動産登記の最大の目的である対抗要件(他者に対して所有権を主張できる)の問題とはなりません。その意味では、所有権保存登記を行うメリットはありません。
一方、「建物について最初に行う権利の登記」という性質から、建物について他の登記を行おうとするのであれば、保存登記を行っていなければ他の登記を入れることができません。例えば、住宅ローンを借り入れたため抵当権設定登記を入れる、売却に伴い所有権移転登記を行う、などについても所有権保存登記を前提として行っておかなければこれらの登記を入れることはできません。
(費用例)
*建物を新築したときに、費用節約のため所有権保存登記を省略していたが、数年経ち、
今後のために建物(評価額1300万円)へ所有権保存登記を入れる場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 所有権保存登記申請 | 3万円 | ||
| 登録免許税 | 1万9500円 | 住宅家屋の軽減税率適用がある場合 評価額の0.15% |
|
| 住宅用家屋証明書 | 1300円 | ||
| 登記簿事前調査 | 335円 | 335円/1通 | |
| 登記事項証明書 | 600円 | 600円/1通 | |
| 合計 | 3万円 | 2万1737円 | 相談料込 |
銀行員は、その都度「お知り合いの司法書士はいらっしゃいますか?」という事を聞きません。銀行員は、当然の様に提携司法書士へ登記を依頼し、司法書士は、ご本人に登記費用を請求しますので、費用の適否を十分に検討する余地がありません。
住宅ローンを借り入れる際には、司法書士に事前に見積もりをとられる事をお勧めしております。また、事業資金を借り入れるために自社物件や経営者の方の所有物件に抵当権を設定する場合についても合わせてお気軽にお問い合わせください。
(費用例)
*住宅ローンとして金融機関から800万円を借り入れ、土地及び建物に抵当権を設定する場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 抵当権設定登記申請 | 4万円 | ||
| 登録免許税 | 8000円 | 住宅家屋の軽減税率適用がある場合 債権額の0.1% |
|
| 住宅用家屋証明書 | 1300円 | ||
| 登記簿事前調査 | 670円 | 335円/1通 | |
| 登記事項証明書 | 1200円 | 600円/1通 | |
| 合計 | 4万円 | 1万1174円 | 相談料込 |
(費用例)
*事業資金として金融機関から5000万円を借り入れ、自社工場及び土地に抵当権を設定する場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 抵当権設定登記申請 | 4万円 | ||
| 登録免許税 | 20万円 | 債権額の0.4% | |
| 登記簿事前調査 | 670円 | 335円/1通 | |
| 登記事項証明書 | 1200円 | 600円/1通 | |
| 合計 | 4万円 | 20万1874円 | 相談料込 |
また、抵当権抹消登記も、抵当権設定登記と同様、ご本人が何も言わなければ、銀行の提携司法書士に登記申請を回されます。司法書士費用のお見積もり等についても、お気軽にお問い合わせください。
(費用例)
*30年支払ってきた住宅ローンを完済し、土地及び建物に設定されている抵当権を抹消する場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 抵当権抹消登記申請 | 1万円 | ||
| 登録免許税 | 2000円 | 1000円/1物件 | |
| 登記簿事前調査 | 670円 | 335円/1通 | |
| 登記事項証明書 | 1200円 | 600円/1通 | |
| 合計 | 1万円 | 3874円 | 相談料込 |
手続上、新たな借入先から融資を受けた金額によって、旧借入先への残債務を一括返済するため、抵当権設定登記及び抵当権抹消登記の登記を行う必要がございます。なお、借り換えをご検討されている方においては、住宅ローン元利金の総額だけではなく、金融機関の手数料、保証料、借換登記費用を踏まえた上で、「有利な条件への変更」となるか否かを検討する必要がございます。
(費用例)
*住宅ローンの借り換えを行い、自宅の土地建物に設定されている抵当権の残債務を一括弁済し、
新たに600万円の抵当権を設定する場合。
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 抵当権設定登記申請 | 4万円 | ||
| 登録免許税(設定) | 2万4000円 | 債権額の0.4% | |
| 抵当権抹消登記申請 | 1万円 | ||
| 登録免許税(抹消) | 2000円 | 1000円/1物件 | |
| 登記簿事前調査 | 670円 | 335円/1通 | |
| 登記事項証明書 | 1200円 | 600円/1通 | |
| 合計 | 1万円 | 2万6526円 | 相談料込 |
休眠担保権の抹消方法は、
①債権者(又は承継者)の存否
②債務の存否
③時効消滅の可能性
④少額の支払による弁済(供託)の可否
⑤特別代理人・不在者管理人等の選任の要否
これらを検討し、最善の方法を具体的にご提案いたします。

会社を設立する事は誰にでもできます。しかしながら、永続・発展する会社に成長させる事ができるのは一握りの経営者です。現に、設立後1年以内に60%、5年以内に85%の会社が倒産しています。
会社法及び商業登記法に精通する司法書士として、会社設立から、会社設立後の各種法律文書の作成、チェック、企業と法律に関するご相談まで、中小企業の経営者の方々を誠実かつ迅速にサポートして参ります。
また、中小企業の経営者と共に、経営理念を作成し、経営ビジョン、経営計画を策定するサポートも行っています。お気軽にご相談ください。
定款の作成、事業目的、出資の目的物及び金額、役員構成、機関構成等の各種打ち合わせから会社設立登記申請まで、設立に必要な手続きを一括でサポートいたします。当事務所は、電子定款認証嘱託に対応しておりますので、ご本人が公証役場に赴いて定款認証を行う場合よりも、印紙代4万円を節約する事が可能です。
また、会社設立後に司法書士と同様、必ず中小企業経営者の片腕となる信頼できる税理士や社会保険労務士の先生も必要に応じてご紹介いたします(紹介料は一切頂いておりません)。
(費用例)
*株式会社設立。役員3名、出資金150万円、発行株式は全て譲渡制限株式の場合。
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 株式会社設立登記申請 | 10万円 | 関係書類作成報酬込 | |
| 登録免許税 | 15万円 | ||
| 定款認証 | 5万2000円 | ||
| 登記事項証明書 | 600円 | ||
| 印鑑証明書 | 450円 | ||
| 合計 | 10万円 | 20万3050円 | 相談料込 |
また、従前の役員が任期満了後再任する場合も、重任の登記を行わなければなりません。
登記すべき期間は、変更事由が生じてから2週間以内と法定(会社法第915条)されており、これを過ぎると、裁判所の決定に応じて過料を支払わなければなりません。(*実際には、2週間を少しでも遅れたら過料に処されるというものではなく、1~2ヶ月ほど過ぎても過料とならない場合もあります。)
(費用例)
*取締役3名(うち、1名は代表取締役を兼ねる)全員の重任登記
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 役員変更登記申請 | 1万5000円 | 関係書類作成報酬込 | |
| 登記事項追加報酬 | 6000円 | 2000円/1名 | |
| 登録免許税 | 1万円 | ||
| 連絡用切手代 | 600円 | ||
| 合計 | 2万1000円 | 1万600円 | 相談料込 |
登記事項は法律に定められており、本店所在場所、商号(社名)、事業目的、資本金の増額や減額等がこれにあたります。
なお、これらの変更方法は、会社法に定められており、株主総会決議を行う場合、取締役の決定で行う場合、官報公告が必要な場合などそれぞれ異なります。
適法かつスムーズに、変更手続きを行うために、決議機関の決定から登記申請までのフロー設計、関係書類作成及び登記手続を一括してサポートいたします。
(費用例)
*福岡市内から福岡市内の本店移転
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 本店移転登記申請 | 2万円 | 関係書類作成報酬込 | |
| 登録免許税 | 3万円 | ||
| 登記事項証明書 | 600円 | ||
| 合計 | 2万円 | 3万600円 | 相談料込 |
*資本金を減額して、1000万円から800万円とする場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 減資登記申請 | 3万円 | 関係書類作成報酬込 | |
| 登録免許税 | 3万円 | ||
| 官報公告 | 1万円 | 12万1632円 | |
| 登記事項証明書 | 600円 | ||
| 合計 | 4万円 | 15万2232円 | 相談料込 |
会社登記を閉鎖(終了)させるためには、まず「解散」の登記を行う事で事業を終了させ、残った債務を債権者に対して支払い、残った財産を株主に配当する「清算」の手続きを行わなければなりません。全ての清算手続が終了した段階で、「清算結了」の登記を行います。(*なお、残った債務を支払うことができない場合には、法人破産や特別清算等の法的な倒産手続きを経る必要があります。)
(費用例)
*会社の廃業に伴い、会社の解散から清算結了登記までを行う場合
| 司法書士報酬(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 解散及び清算人選任登記 | 3万円 | 関係書類作成報酬込 | |
| 登録免許税(解散) | 3万9000円 | ||
| 官報公告料 | 1万円 | 3万8764円 | |
| 清算結了登記 | 3万円 | 関係書類作成報酬込 | |
| 登録免許税(清算) | 2000円 | ||
| 登記事項証明書 | 600円 | ||
| 合計 | 7万円 | 8万364円 | 相談料込 |
M&Aには、下記の方法があり、いずれの方法が適切かは各会社の事情(業績、技術、営業力、従業員、歴史、将来設計等)により判断します。
準備段階での秘密保持契約に始まり、相手先とのM&A契約、双方の議決、債権者保護手続き、登記手続き等、M&Aにかかるフローチャートを作成し、適切かつ円滑にM&Aが行われるよう、一括してサポートを行います。
〔会社の全部を売り買いする方法〕
| ① 合併 | 会社の全資産及び負債、従業員等をそのまま相手先会社に売却する手法で、 吸収合併と新設合併の方法があります。 |
|---|---|
| ② 株式の売却 | 旧経営者が所有している株式を第三者に譲渡する方法で、株主構成のみが 変更されるため従業員等の内部構成は従前と変わりません。 |
| ③ 株式交換 | 自社の株式と他社の株式を交換する方法で、 売手会社が買手会社の100%子会社となる方法です。 |
〔会社の全部を売り買いする方法〕
| ① 会社分割 | 複数の事業部門を有する会社が、その一部を分離させて他の会社に売却する方法です。 新設分割と吸収分割の2種類の方法があります。 |
|---|---|
| ② 事業譲渡 | 個別の事業(工場や機械のみならず、ノウハウや知的財産権、 顧客等事業に必要な要素を含む)を売却する方法です。 |
経営者が判断能力を失ったり、亡くなったりする前に、適切に事業承継を行う事で、会社株式、経営権、債権者対応、内部構成を整備し、会社の永続をサポートします。
〔事業承継の方法〕
| ① 親族内承継 | 中小企業の半数以上が行う方法であり、関係者からの理解が得られやすい方法です。 |
|---|---|
| ② 従業員や外部への承継 | 企業の内外から適任者を広く求める事ができる方法です。 |
| ③ M&A | 前記「M&A」をご参照ください。 |
また、資本主義社会の商取引では、自己に有利な契約を締結しようとするため、相手方の提案した契約書にただ押印をするという事を何も疑わずに、自社にとって不利益な契約を締結している中小企業が非常に多いのが現状です。
法令を遵守することは企業を守る事です。そして自社に有利な契約を締結することは、経営者の会社に対する責任です。しかしながら、人的物的資源の限られている中小企業においては、自社に法務専門部署を設けることは困難です。
当事務所は、中小企業経営者のための法務パートナーとして、法律文書の作成、リーガルチェック、個別・継続法務相談等により、会社の永続発展のためのサポートをいたします。
経営理念を成文化して、会社内外に示すことで、経営者及び従業員が1つの方向を向いて事業を進めることができると共に、顧客に対して自社の存在意義を示すことができます。しかし、経営理念を定めなかったり、誤った経営理念の定め方をしてしまうと、誤った価値観で経営を行い、外部からの信用を失ったり、社内風土を壊してしまうことにも繋がります。
正しい健全な価値観を社内で共有し、顧客に信頼される会社として企業が永続するためには、経営理念の策定は不可欠のものです。
当事務所では、経営者の方々と深くコミュニケーションを図り、漠然と思い描いている会社の方向性、理想とする社内環境、顧客や取引先との関係性を明確にし、御社の経営理念策定のサポートを行います。